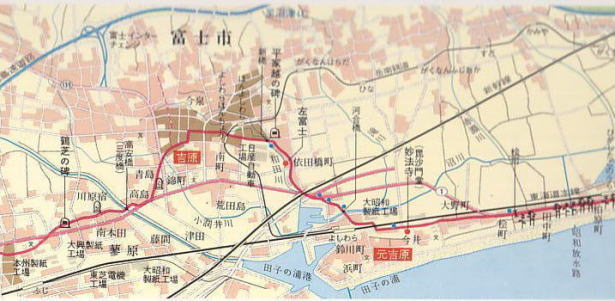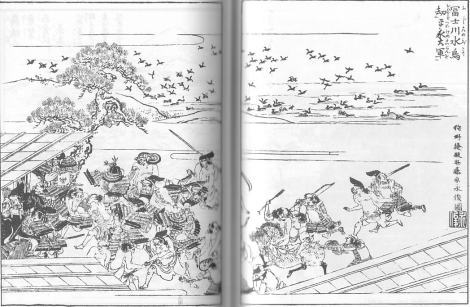「歩く会」の二日目は、一転、雨中の行進で始まった。
「歩く会」の二日目は、一転、雨中の行進で始まった。ホテルのバスで原宿へ戻り、再び富士駅に向かった。
一歩一歩足もとの水溜りに注意しながら進んだ。
出勤を急ぐ車の飛沫にも気をつけねばならなかった。
しかし今は道路が舗装されている。昔は泥んこ道を
裸足で歩いたのだと思うと、何でもなかった。
昔は、カラカラ天気でも風が吹けば大変であった。
『名所記』に次のような記述がある。
<間門町、諏訪町、松長町、道中砂地にて、風の立つ
ときは、目もあかれず。まして、砂原は三里ゆけば二里
もどるとかや。道ばかのゆかぬ者也。>


 左も広重と同時代の渓斎英泉(1791~1848)が、「原ノ驛」
左も広重と同時代の渓斎英泉(1791~1848)が、「原ノ驛」