2016.05.03.〜 05.
薫風香る五月 楽しかった三日間
1 5月3日 (憲法記念日)
今日は大船の県立フラワー・センターへ出掛けた。
淡青会の高津有二さんが主宰されている「クレマチス展」を見るためである。
好天に恵まれたので家から歩いて行ったら、1時間半近くかかった。少し草臥れた。
一服してから展示会を覗いた。
昨年同様、素晴らしい作品が並んでいた。
既に、淡青会の仲間が数名来られて居て、しばらく言葉を交わした。
この日は、園長ご推薦の「ハンカチの木」も目当てにしていた。
その花も真っ盛りで嬉しかった。初めて知った木だったが、花は清楚で、名が愉快だった。
ボタン園やシャクナゲ園をひと通り見て遊んだあと、温室に入った。
人智では到底及ばないこの不思議な花々は、一体どうして誕生するのだろうか。
あらためてこの数年問い続けている謎を思った。
昨今は、宇宙の誕生、地球の誕生、生命の誕生、が全て同じ原理に基づいていると教えられて、
あらためて驚きを禁じ得ないのである。
折しも今日は「憲法記念日」。
『憲法改正の経緯』や、『憲法9条についての僕の立場』を考えた。
昨今頻繁に行われている世間の議論に、僕は何となく物足りなさを感じている。
先日突然知った、南原晃さんの訃報を契機に、『丸山昌男 回顧談』のことも思い出した。
2 5月4日 (みどりの日)
この日は久し振りに円覚寺に参禅し、横田大老師の『臨済録提唱』を拝聴した。
この三日間は、国宝の舎利殿が公開されているので、それもゆっくり見学した。
仏殿の裏にある「ヒトツバタゴ=なんじゃもんじゃの木」の花が真っ盛りであった。
「ヒトツバタゴ」の事は、一道師のブログで教えられた(上右写真)。
舎利殿には、お釈迦様の歯牙が祀られている。
鎌倉の三代将軍源実朝公が、宋の時代に、中国の能仁寺から請来されたものである。
建物は廃寺になった太平尼寺の仏殿が移されて来た。「唐様」と呼ばれる独特の建築様式
については、我々は國民學校時代から教えられたので馴染みが深い。
長男が小さかった頃二人で道を間違えて、うっかり裏山から舎利殿に迷い込んだ記憶もある。
3 5月5日 (こどもの日)
この日は、葉山の 「しおさい公園」 を訪ねた。
一年ぶりに節句の具足を飾り、明月谷の緑を堪能していたら、久し振りに海を見たくなった。
「しおさい公園」は、昭和62年に開設された。
大正天皇が崩御され昭和天皇が皇位を継承された土地、言わば「昭和発祥の地」の一部が
葉山町に下賜され、昭和が終わる前年に公園として整備され博物館も完成したのであった。
昭和天皇は海洋生物の研究がご趣味であったので、しばしばこの御用邸にお出でになった。
博物館では、「タイ」とつくけど「鯛」ではない「タイ」 と題した企画展が行われていた。

縄文時代の遺跡から「マダイ」の歯や骨が出土すること
から、「マダイ」は古くから日本に生息した魚類である。
魚名の由来は、魚体が平らであるため延喜式などで、
「平魚(たい)」と称されていたことにある。
「鯛」という漢字は、「周」年採集が可能であったからと
の説と、「周」の字は、中国で扁平を表す字であること
から「鯛」になったとする説がある。
何れにせよ、「タイ」という言葉は、「ウオ」と並んで古く
からある言葉である。
ところで、古事記、日本書紀、万葉集などで使われている「タイ」という魚は、「マダイ」のことのみで、
現在「クロダイ」と呼ばれている魚は、「チヌ」と呼ばれていたように、奈良〜平安時代にかけては、
「〜タイ」と呼ばれる和名の魚は「マダイ」の他にはなかった。
江戸時代の畔田翠山(くろだすいざん)が著した「水族志」には、「タヒ」と名の付く魚が19種類記されて
いる。また、奥倉辰行(おくくらたつゆき)の「水族寫眞」には86種類の「タヒ」が記述されている。
この頃から、「タイ」は「ウオ」と同じように魚を示す言葉として使われるようになった。
昭和に入ると「タイ」と名の付く魚はうんと増え、1958年に発表された渋沢敬三の研究では、235
種類の「タイ」が記録されている。又近来は、海域に住む魚のみならず、中東やアフリカの淡水に
すむ魚にまで商品名として、「タイ」の名が付けられるに至っている。
ケースには様々な「タイ」が展示されていた。人間様のご都合で、「タイ」の数は幾らでも増え続ける。
お昼のお弁当を買いにスーパーに寄ったら、「季節の香り」の「しょうぶ」が目についた。
今日は「端午の節句」。早速それを求めて帰り、夜は「菖蒲湯」にして楽しんだ。
「暦」では、今日は早くも 「立夏」 を迎えていた。
つい最近まで巣の中で親を待ち続けたツバメの子も、今日は一人で電線に止まっていた。
五月は心地良い月である。
昭和天皇のお写真を葉山で見て、ふと父のことを思い出した。
父は昭和天皇と同じ明治34年(1901)の生まれで, 此の年は20世紀が始まった年である。
父の誕生日=5月11日を2倍すると10月22日になる。この日は小生の誕生日である。
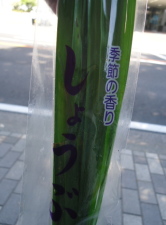

五月(さつき)こそ 男(おのこ)の月ぞ この月に 生(あ)れにし父を 羨(とも)しと思ふ 義信